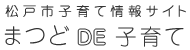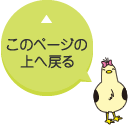児童扶養手当
更新日:2025年11月13日
電子申請・郵送手続きにご協力ください
市役所の窓口等にご来庁いただかなくても手続きができます。
児童扶養手当に関する各種申請・届出は、全て郵送での手続きが可能となっております。また、便利な電子申請による手続きも一部可能となっておりますので、併せてご利用ください。
※必要書類の不備や追加がある場合は、申請受付後に別途ご案内いたします。
便利な電子申請をご活用ください
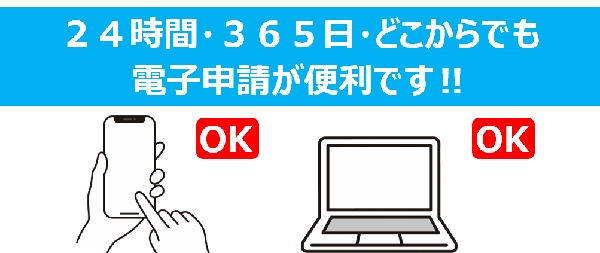
電子申請は、松戸市が運用している「松戸市オンライン申請システム」にて行われ、申請時に入力されたデータは暗号化され送信されます。下記の申請・届出を選択してご利用ください。なお、利用にあたっては、利用者登録が必要ですので、ご了承ください。
- 申請・届出時の不足書類提出(コピーでの提出が可能なもののみ)
- 現況届(児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費等助成)の不足書類(コピーでの提出が可能なもののみ)
- 児童扶養手当証書再交付申請・亡失届
- 金融機関変更届
- 特定者資格証明書 交付申請
- 特定者用定期乗車券購入証明書交付申請
- 受給証明書申請
郵送の場合
〒271-8588 松戸市根本387番地の5
松戸市 子ども未来応援課 児童給付担当室(児童扶養手当担当)
制度概要
児童扶養手当は、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給資格者
手当を受けることができる人は、子どもを監護している母、子どもを監護し、かつ、生計を同じくする父、または父母に代わって子どもを養育している人(子どもと同居している祖父母等)で、監護・養育する子どもが次の受給要件のいずれかにあてはまる人です。
なお、子どもとは18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある人ですが、子どもの心身に児童扶養手当法施行令別表第一(PDF:119KB)に定める障害※がある場合には、20歳の誕生日の前日の属する月まで手当を受けることができます。国籍は問いませんが、外国籍の人は、一定の在留資格がある人に限ります。
※児童扶養手当法施行令別表第一(PDF:119KB)に定める程度の障害とは、国民年金法による障害等級の1級及び2級、身体障害者福祉法による障害等級の1級、2級、3級及び4級の一部、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の別表に定める障害の程度に該当するものがこれに相当します。詳細はお問合せください。
受給要件
- 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が重度の障害の状態※にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている子ども
- 父または母がDVにより保護命令を受けた子ども
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
- その他、生まれたときの事情が不明である子ども
※父または母が重度の障害の状態とは、児童扶養手当法施行令別表第二(PDF:116KB)に定める障害をいいます。
児童扶養手当法施行令別表第二(PDF:116KB)に定める障害とは、国民年金法及び厚生年金保険法による障害等級の1級、身体障害者福祉法による障害等級の1級及び2級の一部に該当するものがこれに相当します。詳細はお問合せください。
ただし、下記の内容に該当する場合は、資格を得られません
子どもが以下に該当する場合
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉施設(保育所や通園施設等を除く)に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者に養育されているとき(配偶者には事実上の婚姻・内縁関係を含む)
※事実上の婚姻とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(頻繁な定期的訪問かつ生計費の補助など、同居の有無は問わない)が存在することをいいます。
父、母または養育者が以下に該当する場合
- 日本国内に住所を有しないとき
支給月額と支給時期
手当の支給日
認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
支給は奇数月の年6回で、支払月の前月までの2ヶ月分が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
| 支給月 | 対象月 |
|---|---|
| 1月 | 前年11月分から12月分まで |
| 3月 | 当年1月分から2月分まで |
| 5月 | 当年3月分から4月分まで |
| 7月 | 当年5月分から6月分まで |
| 9月 | 当年7月分から8月分まで |
| 11月 | 当年9月分から10月分まで |
※支給日は原則各支給月の11日です。ただし、土曜・日曜・祝日・休日にあたる場合は、その直前の金融機関が営業している日となります。
児童扶養手当の額
児童扶養手当の額は受給者の所得額に基づいて決定されます。認定請求者の所得が制限額以上であるときは、手当の全部または一部が支給されません。また、請求者の配偶者や扶養義務者の所得が制限額以上である場合は、支給されません。
※毎年11月から翌年10月までを支給年度とし、支給年度単位で手当の額を決定します(平成31年度から)。
令和7年4月分以降の手当月額
| 子ども1人のとき | 46,690円 |
|---|---|
| 子ども2人のとき | 57,720円 |
| 子ども3人のとき | 68,750円 |
4人以上の場合、1人につき11,030円が加算されます。
| 子ども1人のとき | 46,680円から11,010円まで10円単位 |
|---|---|
| 子ども2人のとき | 57,700円から16,530円まで10円単位 |
| 子ども3人のとき | 68,720円から22,050円まで10円単位 |
4人以上の場合、1人につき11,020円から5,520円まで10円単位が加算されます。
所得制限
児童扶養手当には所得制限があります。
受給者本人または配偶者及び扶養義務者の前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得額により、下記のとおりに分かれます。
- 全部支給の人
- 一部支給の人
- 全部支給停止の人
※所得が制限額以上ある場合は、その支給年度(11月分から翌年10月分まで)の手当は全部または一部が支給停止となります。
所得額の計算方法
所得額は以下の計算式で算出されます。
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除等)+養育費の8割相当額-8万円-10万円(注釈1)-諸控除(医療費等)
(注釈1)10万円の控除は、給与所得又は年金所得がある場合に限ります。(事業所得のみの場合は、控除されません)
養育費
子どもが父または母から支払いを受けた養育費の金額、及び受給資格者が父または母から支払いを受けた養育費の金額の8割を所得に加算します。
養育費とは、次の要件のすべてに当てはまるものをいいます
- 児童扶養手当の受給資格者が監護している子どもの父または母から支払われたもの
- 受け取った者が受給資格者または子どもであること
- 父または母から受給資格者または子どもに支払われたものが金銭、有価証券(小切手、株券、商品券など)であること
- 父または母から受給資格者または子どもへの支払い方法が、手渡し、郵送、受給資格者または子ども名義の銀行口座への振り込みであること
- 養育費、仕送り、生活費、自宅などのローンの肩代わり、家賃、光熱費、教育費など子どもの養育に関係のある経費として支払われていること
8万円
社会保険料、生命保険料、損害保険料等の相当額として一律に8万円を控除します。
諸控除
控除項目及び控除額は下記のとおりです。
| 控除項目 | 控除額 |
|---|---|
障害者控除 |
27万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
雑損控除 |
当該控除額 |
医療費控除 |
当該控除額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
当該控除額 |
配偶者特別控除 |
当該控除額 |
寡婦控除 |
27万円 |
ひとり親控除 |
35万円 |
※児童扶養手当の所得計算上は、受給資格者が母の場合は寡婦控除・ひとり親控除が、父の場合はひとり親控除は適用されません。
所得制限額表
| 扶養親族等の数 | 父、母または養育者 (全部支給) |
父、母または養育者 (一部支給) |
扶養義務者、 配偶者、 孤児等の養育者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
| 1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 |
| 2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 |
| 3人 | 183万円未満 | 322万円未満 | 350万円未満 |
| 4人 | 221万円未満 | 360万円未満 | 388万円未満 |
| 5人 | 259万円未満 | 398万円未満 | 426万円未満 |
| 扶養親族等の数 | 父、母または養育者 (全部支給) |
父、母または養育者 (一部支給) |
扶養義務者、 配偶者、 孤児等の養育者 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 142万円未満 | 334.3万円未満 | 372.5万円未満 |
| 1人 | 190万円未満 | 385万円未満 | 420万円未満 |
| 2人 | 244.3万円未満 | 432.5万円未満 | 467.5万円未満 |
| 3人 | 298.6万円未満 | 480万円未満 | 515万円未満 |
| 4人 | 352.9万円未満 | 527.5万円未満 | 562.5万円未満 |
| 5人 | 401.3万円未満 | 575万円未満 | 610万円未満 |
一部支給額の計算方法
一部支給は所得額に応じて月額46,680円から11,010円(子どもが1人の場合)の間で、10円単位の額となります。次の計算式で算出されます。
- 令和7年4月分以降
【第1子】
手当額=46,680円-(受給者の所得額-所得制限額※)×0.0256619
【第2子以降加算額】
手当額=11,020円-(受給者の所得額-所得制限額※)×0.0039568
※所得制限額は扶養親族等の数に応じて変わり、所得制限額表の「父、母または養育者」欄の「全部支給」の金額です。
次の表は上記の計算式で算出した例です。母子または父子家庭で扶養親族等が1人、児童扶養手当の対象となる子どもが1人の場合の所得額に対応する手当月額です。
| 所得額(例) | 手当月額(例) |
|---|---|
| 107万円 | 46,680円 |
| 130万円 | 40,780円 |
| 160万円 | 33,080円 |
| 190万円 | 25,380円 |
220万円 |
17,680円 |
| 240万円 | 12,550円 |
申請方法
下記の必要書類を準備し、子ども未来応援課児童給付担当室窓口または郵送にて認定請求の手続きをしてください。
各支所・市民課の窓口では受付しておりません。
手続き終了後、審査を経て結果通知を送付しますが、審査には通常2、3ヶ月を要します。
手当の認定に際しての所得制限等の詳細は、子ども未来応援課児童給付担当室(047-366-3127)にお問い合わせください。
主な必要書類の例
| 必要な書類 | 詳細内容 |
|---|---|
| 記入例(PDF:553KB) | |
戸籍全部事項証明書原本 |
※本籍地が松戸市の場合、戸籍謄本を発行する際に「児童扶養手当」の申請に使用することを申し出ていただきますと、発行手数料が無料となります。
|
| 金融機関通帳の写し | 金融機関・支店・口座番号・名義人のわかる部分 |
| 家屋に関する書類の写し |
|
| 養育費に関する書類 | 公正証書や協議書など |
| その他 | 申請者の受給要件や生活状況によって必要書類が異なるため、事前に必要書類および申請可能時期などの案内を受けてください。 |
| 松戸市ひとり親家庭等医療費等助成資格登録申請書(PDF:120KB) | 記入例(PDF:465KB) |
※申請事由が離婚の場合、離婚届受理証明書、調停証書、審判書または判決書の謄本(確定証明書を添付)で仮申請することもできます。ただし、後日戸籍謄本も提出していただきます。
必要な届け出
現況届の提出
毎年8月1日から8月31日までの間に、郵送等で行います。所得状況や加入保険の状況等を所定の用紙で届け出るもので、資格の継続に不可欠です。
この届出がないと当年11月以降の手当が受けられないほか、2年以上提出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなりますのでご注意ください。
手当を申請した人の届出義務
| 必要な届出 | 詳細内容 | 電子 |
|---|---|---|
受給資格がなくなるとき(以下例)
|
なし | |
市内で転居したとき
※名義が本人以外の場合や、個人間契約の場合等は追加で書類をお願いする場合があります。 |
なし | |
市外に転出するとき(転出先で婚姻(事実婚)となる場合は、喪失届が必要です。) |
なし | |
| 再交付申請書・亡失届(PDF:64KB) | 児童扶養手当証書をなくしたときや破損したとき | あり |
| 金融機関変更届(PDF:121KB) | 振込先の金融機関を変えるとき(受給者名義のみ) |
あり |
養育する子どもが増えたとき |
なし | |
| 対象となる子どもが減った場合など | なし | |
対象児童に係る変更があったとき
|
なし | |
| 氏名変更届(PDF:121KB) | 受給者の氏名が変わったとき |
なし |
| 支給事由変更届(PDF:121KB) | 受給中に離婚した場合など |
なし |
| 支給停止関係届(PDF:92KB) | 受給者が所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき | なし |
| 公的年金給付等受給状況届(PDF:101KB) | 公的年金給付等を申請するときや受けることができるとき |
なし |
※資格がなくなっているにもかかわらず、届出をしないで手当を受給した場合、資格がなくなった翌月からの手当は遡って全額返還していただきます。ご注意ください。
一部支給停止措置【養育者を除く】
受給者に就業が困難な事情がないのに就業意欲がみられない場合、手当の支給額の2分の1が停止されます。手当を受けてから5年、または受給要件に該当した月から7年を経過したときは、この措置の対象となります。
対象者には毎年6月末頃、これに関する通知が送付されます。
※提出期限を過ぎると、提出された日の属する月の前月までの手当の2分の1が停止されますのでご注意ください。
一部支給停止措置(減額)を受けないためには
この措置は、下記の一部支給停止適用除外事由に該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類を提出することにより適用を除外する(今までどおりの金額を受け取る)ことができます。
対象となる方には、別途お知らせを送付いたします。
一部支給停止適用除外事由
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷または疾病等により就業することが困難である
- 受給資格者が監護する子どもまたは親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である
身内が亡くなった場合の手続きについて
| 亡くなった方 | 受給者の場合 | 対象児童の場合 |
|---|---|---|
| 申請・届出 | 児童扶養手当受給者死亡届・未支払児童扶養手当請求書(PDF:93KB) | |
| 手続きができる方 | 同居親族者 | 同居親族者 |
| 必要な持ち物 |
|
手続き者の本人確認書類 |
※なお、死亡した方の遺児を祖父母等が養育される場合は、以下の手当の受給が可能なことがございます。詳細は、それぞれのページをご覧ください。
その他
JR通勤定期券の割引の利用方法
証明書の発行までにお時間をいただきます。お早めにご申請ください。
1.「特定者資格証明書」の交付申請を子ども未来応援課児童給付担当室窓口または郵送または電子申請で行う
必要なもの
- 特定者資格証明書交付申請書(PDF:100KB)
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 児童扶養手当証書
- 通勤定期券を購入する人の証明写真(最近6ヶ月以内に撮影した縦4センチメートル×横3センチメートルのもの)(電子申請の場合は写真データを添付してください)
- 委任状(交付対象者本人以外が窓口に来られる場合は、対象者から代理人への委任状と、それぞれの顔写真付きの本人確認書類の写しが必要です)
2.「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付申請を子ども未来応援課児童給付担当室窓口または電子申請(電話可)で行う
必要なもの
- 特定者資格証明書
- 委任状(交付対象者本人以外が窓口に来られる場合は、対象者から代理人への委任状と、それぞれの顔写真付きの本人確認書類の写しが必要です)
3.JRの駅の窓口で定期券を購入する
必要なもの
- 特定者資格証明書
- 特定者用定期乗車券購入証明書
※1 児童扶養手当が全部支給停止の人は対象になりません。また資格証明書の有効期間は1年間で、更新する場合は再度上記1の手続きが必要です。
※2 特定者用定期乗車券購入証明書の有効期間は発行日より原則6ヶ月です。ただし発行時の申請者のご状況(※)によっては、期間が短くなる場合がございます。
(※)児童扶養手当の受給状況、お持ちの特定者資格証明書の有効期限 等
受給証明書
今まで受給した児童扶養手当の金額などの証明を受ける場合は、子ども未来応援課児童給付担当室窓口・郵送・電子申請にて申請してください。
1週間程度で受給証明書を送付いたします。
必要なもの
- 受給証明申請書(PDF:112KB)
- 本人確認書類の写し
児童扶養手当Q&A
- 前年所得額が所得制限を超えている場合は認定請求できないのでしょうか?
認定請求できます。所得制限額を超えていても、受給要件に該当していれば受給資格が認定されます。今後、現況届等で所得制限額を超えていないことが確認されたときから手当が支給されます。
- 両親と一緒に暮らしていますが、所得制限にあたって両親の所得も審査されるのでしょうか?
この場合、原則として両親と同居であれば生計同一と推定されるので両親の所得も審査します。生計同一とは、消費生活上の家計が同一であることをいいますが、同居している場合でも例外的に生計が別として、両親の所得を審査しないこともあります。その場合、生計が別であることを証明する書類(それぞれの公共料金の請求書、家屋の平面図など)の提出が求められます。
- 孫の両親がいないので孫の面倒をみています。児童扶養手当をもらえますか?
養育者として受給できる可能性がありますので、ご相談ください。
- 事実婚とはどんなものですか?
事実婚とは、児童扶養手当法上の独特の概念で、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(頻繁な定期的訪問、定期的な生計費の補助など、同居の有無を問わない)が存在することをいいます。例えば、法律によって婚姻が認められない場合であっても、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在するときには、事実上の配偶者がいることにかわりないので事実婚に該当します。判断に際しては、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りや書類の提出を求められることがあります。
- 未婚の母子ですが、子どもは父親に認知されています。子どもが認知されると手当を受けられないのでしょうか?
平成10年8月1日から未婚の母子について、子どもが認知されても手当を受けることができるようになりましたので、手当を受給したいときは認定請求の手続きをしてください。
- 現在、児童扶養手当の所得制限を超えているため手当を全部支給停止されています。こうした場合でも、現況届を提出しなければならないのでしょうか?
現況届を提出しないと、その後所得制限に該当しなくなっても、手当が受けられなくなる場合がありますので、全部支給停止されている場合でも必ず提出してください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。