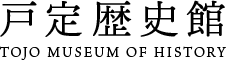徳川慶喜・昭武関係年表 一
更新日:2015年9月17日
1837年(天保8年)9月29日~1869年(明治2年)9月28日
| 西暦 | 元号 | 月日 | 年齢 | 慶喜関係記事 | 年齢 | 昭武関係記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1837年 | 天保8年 | 9月29日 | 1 | 水戸藩九代藩主斉昭の七男として江戸小石川水戸藩上屋敷に生まれる、母は有栖川吉子、幼名七郎麿、昭致 | ||
| 1838年 | 天保9年 | 4月28日 | 2 | 水戸に行き、水戸で養育される | ||
| 1847年 | 弘化4年 | 9月1日 | 11 | 一橋家の養子になり、家督を相続する | ||
| 1848年 | 弘化4年 | 12月1日 | 11 | 元服し、名を慶喜と改める。 | ||
| 1848年 | 嘉永元年 | 12月4日 | 12 | 一条忠香の娘千代と婚約 | ||
| 1848年 | 嘉永元年 | - | 12 | (徳川斉昭)家臣菊池忠を長崎に派遣し、写真術を研究させたという説がある*3 | ||
| 1849年 | 嘉永2年 | 5月6日 | 13 | (島津斉彬)印影鏡について徳川斉昭に書簡を送る*3 | ||
| 1849年 | 嘉永2年 | 6月7日 | 13 | (島津斉彬)同じく印影鏡について徳川斉昭に書簡を送る*3 | ||
| 1850年 | 嘉永3年 | 7月27日 | 14 | (島津斉彬)印影鏡訳術に関する書簡を徳川斉昭に送る*3 | ||
| 1853年 | 嘉永6年 | 2月6日 | 17 | 千代との婚約を破棄、五月一条忠香の養女美賀子と婚約 | ||
| 1853年 | 嘉永6年 | 9月24日 | 1 | 斉昭の十八男として江戸駒込の水戸藩中屋敷に生まれる、母万里小路睦子、幼名余八麿昭徳、字子明、号鑾山 | ||
| 1854年 | 安政1年 | - | 18 | (徳川斉昭)藩士菊池冨太郎を長崎へ留学させ、写真術を研究させたと伝えられる*3 | ||
| 1856年 | 安政2年 | 12月3日 | 20 | 美賀子と結婚、参議に任じられる | ||
| 1857年 | 安政4年 | 3月24日 | 21 | 幕府秘蔵のライフル銃を借り受け拝見する(『新稿一橋徳川家記』) | ||
| 1859年 | 安政6年 | 8月27日 | 23 | 幕府より隠居謹慎を命じられる。 | ||
| 1860年 | 万延元年 | 6月29日 | 24 | (徳川斉昭)水戸城中にて急死、烈公と諡される | ||
| 1860年 | 万延元年 | - | 24 | アメリカ人写真師某、遣米使節随行員を撮影しガラス写真七十枚と覗目鏡を贈る、後、これらを徳川慶喜に献上 | ||
| 1862年 | 文久2年 | 7月6日 | 26 | 一橋家再相続を命じられ、将軍後見職に就く | ||
| 1862年 | 文久2年 | - | 26 | (亀谷徳次郎)京都に上り、御所写真師となる、ついで、知恩院内に写真業を開く*3 | ||
| 1863年 | 文久3年 | 1月10日 | 27 | 御所に参内し、始めて孝明天皇に謁見する | ||
| 1864年 | 文久3年 | 12月21日 | 27 | 京都小浜藩邸(若州屋敷)を宿所とする(慶応3年9月21日まで) | ||
| 1864年 | 文久3年 | 12月30日 | 27 | 朝廷より参豫を命じられる | ||
| 1864年 | 文久4年 | 1月11日 | 12 | 禁裏守衛のため江戸出発、百余人を伴う | ||
| 1864年 | 文久4年 | 1月28日 | 12 | 京都に着く、本圀寺勢は約三百名となる | ||
| 1864年 | 元治元年 | 3月25日 | 28 | 禁裏御守衛総督・摂海防禦指揮を命ぜられる | ||
| 1864年 | 元治元年 | 3月9日 | 28 | 参豫を辞す | ||
| 1864年 | 元治元年 | 4月14日 | 12 | 徳川慶勝に、昭武を松平容保の嗣子にする仲介をさせる。 | ||
| 1864年 | 元治元年 | 5月9日 | 28 | 摂海巡視のため大阪に下る | ||
| 1864年 | 元治元年 | 5月20日 | 28 | 帰京 | ||
| 1864年 | 元治元年 | 7月10日 | 12 | 紀州・松山両藩兵とともに禁裏南門守備の任につく | ||
| 1864年 | 元治元年 | 7月19日 | 28 | 禁門の変で諸藩を指揮 | 12 | 禁門の変に際して一橋家床几隊と供に日華門を守備 |
| 1864年 | 元治元年 | 8月5日 | 12 | 本圀寺瑞雲院へ移る | ||
| 1864年 | 元治元年 | 11月19日 | 12 | 従五位下侍従に叙任される、28日、民部大輔を兼任 | ||
| 1864年 | 元治元年 | 12月3日 | 28 | 天狗党討伐のため京を出発、近江へ向かう、12月26日帰京 | ||
| 1865年 | 元治元年 | 12月4日 | 12 | 天狗党討伐のため本圀寺を出発 | ||
| 1865年 | 元治2年 | 1月3日 | 13 | 本圀寺に凱旋 | ||
| 1865年 | 元治2年 | 1月7日 | 13 | 慶喜の若州屋敷に年賀に赴く | ||
| 1865年 | 元治2年 | 1月23日 | 13 | 天狗党追討の功に対し、朝廷より賞詞を賜わる*4 | ||
| 1865年 | 慶応元年 | 4月7日 | 29 | 慶応と改元 | ||
| 1866年 | 慶応元年 | 12月7日 | 14 | 朝廷より千両賜わる沙汰ある*4も、辞退 | ||
| 1865年 | 慶応元年 | - | 29 | (内田九一)大阪天満に写真業を開く、また、大阪城内兵士の西洋式調練、大阪の風景・風俗を撮影する*3 | ||
| 1865年 | 慶応元年 | - | 29 | 京都町奉行大久保主膳家臣某(内田九一ともいう)、「二条城歩兵調練之図」(四枚続き)、「慶喜公御滞在京都御旅館(本願寺)之図」などを撮影する*3 | ||
| 1866年 | 慶応2年 | 1月4日 | 14 | 従五位民部大輔の資格で参内、始めて孝明天皇に拝謁*4 | ||
| 1866年 | 慶応2年 | 3月6日 | 14 | 大坂城へ将軍家茂の御機嫌伺いに行く | ||
| 1866年 | 慶応2年 | 3月10日 | 14 | 京都の一橋邸内にて写真撮影 | ||
| 1866年 | 慶応2年 | 7月20日 | 14 | 将軍家茂没、昭徳院と諡されたため昭徳は昭武と改名 | ||
| 1866年 | 慶応2年 | 7月29日 | 30 | 将軍に代わり征長に赴くべしとの勅許が下る | ||
| 1866年 | 慶応2年 | 7月31日 | 30 | 禁裏御守衛総督・摂海防禦指揮を辞す | ||
| 1866年 | 慶応2年 | 8月1日 | 14 | 参内後、一橋邸で慶喜と対面する | ||
| 1866年 | 慶応2年 | 8月8日 | 30 | 長州出陣につき御暇参内、8月11日俄かに出陣を中止 | ||
| 1866年 | 慶応2年 | 8月9日 | 30 | 一橋家徳川家、二条堀川東入町横山榮五郎定職人阿部寿八郎を写真師として抱え入れる。(『新稿一橋徳川家記』) | ||
| 1866年 | 慶応2年 | 8月16日 | 30 | 兵を解き諸大名を召集の上今後の方針を決める事を奏請、8月21日休戦の勅命が下る | ||
| 1866年 | 慶応2年 | 8月20日 | 30 | 徳川宗家を相続、軍制改革などに着手 | ||
| 1866年 | 慶応2年 | 11月14日 | 14 | 昭武を使節としてフランスに派遣し、かつ五年間留学させることを決める | ||
| 1867年 | 慶応2年 | 11月28日 | 14 | 水戸家家老へ徳川昭武のフランス派遣申渡し,また清水家相続を命ぜられる、以後徳川を称す*4 | ||
| 1867年 | 慶応2年 | 12月3日 | 14 | 幕府、昭武を、慶喜の営内に住ませる | ||
| 1867年 | 慶応2年 | 12月5日 | 30 | 征夷大将軍に任じられる | ||
| 1867年 | 慶応2年 | 12月9日 | 14 | 京都警護の功により、従四位下左近衛権少将に叙任*4 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 1月3日 | 15 | 京都出発、兵庫から長鯨丸で横浜へ向けて出帆 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 1月11日 | 15 | 横浜をフランス郵船アルフェ-号で出港*6 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 1月23日 | 31 | 長州征討軍を解く | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 2月29日 | 15 | マルセイユへ到着*6 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 3月1日 | 15 | 昭武一行記念写真撮影*6 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 3月6日 | 15 | マルセイユ出発、リヨンで一泊*6 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 3月7日 | 15 | パリ到着、カピュシン街のグランオテルに投宿 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 3月17日 | 15 | レセップス邸で琉球王国使節を自称する薩摩藩側と幕府と対立、翌日フランス各紙に幕府の国家主権を疑問視する記事掲載される | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 3月24日 | 15 | テュイルリー宮殿で皇帝ナポレオン三世に謁見、国書提出*6 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 3月26日 | 15 | 博覧会会場で各国の産物を見る、皇帝より贈物届く*6 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 3月28日 | 31 | 英蘭仏各国公使と大阪城で公式謁見、同日、イギリス人サットン、慶喜を写真撮影する | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 3月29日 | 31 | イギリス公使、大坂城で慶喜と会見、同日サットン、慶喜を写真撮影する | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 4月4日 | 15 | パノラマを見物 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 5月7日 | 15 | ナポレポン三世の招待を受けロシア皇帝、プロシャ国王とともにベルサイユ宮殿へ行く、夕方帰る*6 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 5月11日 | 15 | ホテルを出てペルゴレーズ街のロシア人貴族の屋敷を借りる | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 5月14日 | 31 | 松平春嶽、山内容堂、島津久光、伊達宗城らと二条城で四侯会議を開く、同日、慶喜、写真師横田彦兵衛に命じて、この四人の肖像写真を撮影させる*3 | 15 | フランスの教育省へ徳川昭武のための教師派遣を申請 |
| 1867年 | 慶応3年 | 5月23日 | 31 | 参内、兵庫開港・長州処分寛大の勅許を求める、夜を徹しての議論の末、翌24日、勅許される | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 5月29日 | 15 | 産業館で万博出品物にたいする賞牌授与式に参列*6 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 6月2日 | 15 | 博覧会を一覧、グランプリ牌を受取る*6 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 6月21日 | 15 | ポルトガル王妃を訪問し、テュイルリー宮殿でナポレオン三世に面会 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 6月29日 | 31 | 幕府、国内事務総裁・会計総裁・外国事務総裁(各新設)陸軍総裁・海軍総裁を任命、老中月番の制を廃止 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 7月11日 | 31 | (西暦8・10)サットン撮影の写真を基にした慶喜の肖像(版画)がイラストレイテッドロンドンニュースに掲載される、慶喜は新しい将軍として紹介される | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 8月6日 | 15 | スイスへ向けてパリを出発、スイスのバ-ゼル着*6 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 8月8日 | 15 | スイス大統領に謁見*6 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 8月16日 | 15 | ベルンを出発、オランダへ向かう*6 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 8月20日 | 15 | 国王ウィレム三世に謁見 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 8月27日 | 15 | ベルギ-のブリュッセル着*6 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 8月28日 | 15 | 国王レオポ-ル二世に謁見 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 9月2日 | 15 | 写真撮影、市内遊覧、夜 観劇 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 9月6日 | 15 | 国王よりテルヴュ-レンでの狩猟に招待される | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 9月12日 | 15 | パリへ戻る*6 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 9月20日 | 15 | イタリアへ向け出発 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 9月21日 | 31 | 二条城に移る | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 9月24日 | 15 | フィレンツェ着、駅よりホテルまで歓迎式典 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 9月27日 | 15 | イタリア国王に面会、夜、観劇 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 10月2日 | 15 | ミラノでイタリア王子に面会 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 10月3日 | 31 | 山内容堂、政権奉還の建議書を提出 | 15 | フレンツェ着*6 |
| 1867年 | 慶応3年 | 10月8日 | 15 | イギリス艦に乗船しマルタ島ヴァレッタ港へ向かう*6 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 10月11日 | 15 | ヴァレッタ港着、軍事施設見学 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 10月14日 | 31 | 大政奉還 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 10月24日 | 31 | 将軍職を辞す。 | 15 | パリ着*6 |
| 1867年 | 慶応3年 | 11月6日 | 15 | イギリスへ向け出発、7日、ロンドン着*6 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 11月7日 | 15 | ド-ヴァ-海峡横断、ロンドン着 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 11月9日 | 15 | 汽車でウィンザ-宮殿へ、ヴィクトリア女王に謁見 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 11月22日 | 15 | ド-ヴァ-港を出発、カレ-を経てパリへ戻る*6 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 11月23日 | 15 | 留学に専念始める、乗馬を日課とする | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 11月25日 | 15 | 乗馬用の馬を購入、洋服を着始める | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 11月26日 | 15 | (西暦12・21)イラストレイテッドロンドンニュースに将軍の後継者になるに違いないと報道される | ||
| 1867年 | 慶応3年 | 12月6日 | 15 | ベルギー国王より贈物の二連銃届く | ||
| 1868年 | 慶応3年 | 12月7日 | 16 | テュルリ-宮殿で皇帝ナポレオン三世に年賀の挨拶、将軍と昭武の写真を贈る | ||
| 1868年 | 慶応3年 | 12月8日 | 16 | 洋服姿で愛犬リヨンとともに写真撮影 | ||
| 1868年 | 慶応3年 | 12月9日 | 31 | 王政復古の大号令 | 16 | フランス皇太子、皇帝の代理で年賀の返礼に昭武を訪問 |
| 1868年 | 慶応3年 | 12月12日 | 31 | 二条城を出て大阪に下る | ||
| 1867年 | 慶応3年 | - | 32 | (田中光顕)父へ慶喜らの写真を送る*3 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | - | 32 | 横浜二四番館のビアト、『万国新聞紙』に大君の写真を一分二朱で販売する旨の広告を出す*3 | ||
| 1867年 | 慶応3年 | - | 32 | ナポレオン三世より鏡玉を贈られ、後これを船橋鍬次郎に与える*3 | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 1月2日 | 16 | 日本から大政奉還の御用状が届く | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 1月3日 | 32 | 鳥羽伏見の戦始まる | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 1月4日 | 16 | スイスより時計届く | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 1月6日 | 32 | 敗報を聞き、大阪城を脱出して海路江戸に向かう | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 1月7日 | 32 | 慶喜追討の勅命下る | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 2月12日 | 32 | 江戸城を出て上野寛永寺に移り謹慎 | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 2月14日 | 16 | 画学教師としてのジェームス・ティソと対面 | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 2月15日 | 16 | この日よりジェームス・ティソに絵を教わる*6 | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 3月1日 | 16 | 飼犬リヨンをシ-ボルトへ差し遣わす | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 3月17日 | 16 | 日本より御用状着く | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 4月5日 | 32 | 中島鍬次郎、慶喜とともに水戸へ行くよう命ぜられる(『続徳川実紀』) | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 4月6日 | 16 | 水戸藩主慶篤死去、しばらく喪を秘す | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 4月8日 | 16 | ブリュッセルで新発明の連発銃を注文 | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 4月11日 | 32 | 江戸城開城、この日慶喜、江戸を出て水戸へ向かう | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 4月9日 | 16 | 今月より水泳を習い始める*6 | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 4月15日 | 32 | 水戸着、弘道館で謹慎 | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 閏4月9日 | 16 | 日本より御用状着く(慶喜の謹慎、上野に過激な者が集結している等の内容)、この時点で昭武は留学を続けたい旨、栗本鋤雲に伝達 | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 閏4月29日 | 32 | 田安亀之助、徳川宗家を相続 | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 5月7日 | 16 | 朝廷より昭武を急ぎ帰国させるよう、水戸藩に命令が下る*4 | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 5月15日 | 16 | 明治政府から昭武一行に対し、帰国の命令書がもたらされる | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 5月15日 | 16 | 日本からの御用状届く、国内情勢が判明する | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 5月16日 | 16 | 慶喜の処遇が決定したことにより、帰国の方針が決定される。 | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 5月17日 | 16 | 慶喜が水戸へ入ったことを日本からの手紙で知る*6 | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 5月17日 | 16 | 日本からの御用状届く、昭武、帰国を決定する | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 5月20日 | 16 | 伊豆守より昭武の早く帰国せよとの書状が出される | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 5月24日 | 32 | 徳川家に駿河遠江七〇万石を賜う | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 5月27日 | 16 | 帰国命令の請書を書き、フリューリー・エラールに託す | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 6月1日 | 16 | 平岡丹羽守以下四名から早期帰国の達書出される | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 7月18日 | 16 | 栗本鋤雲より彰義隊敗北の報届く | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 7月19日 | 32 | 水戸より駿府に移り、宝台院にて謹慎を続ける | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 7月20日 | 16 | 日本より御用状着く、有栖川宮熾仁からの帰国命令 | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 7月22日 | 16 | フランス語教育を中止 | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 7月24日 | 16 | 夕方、ロッシュ・エラール・ヴィレット大佐来訪、帰国に決する旨フランス側に伝える、夜、クーレ来訪 | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 7月 | 32 | 鈴木真一、慶喜の小姓を撮影する*3 | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 8月2日 | 16 | 鉄砲・写真・地図・望遠鏡等買上げ品を決める | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 8月5日 | 16 | 午後、絵の教師ジェ-ムズ・ティソ、昭武の肖像を描く | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 8月6日 | 16 | 水戸藩より迎えの井坂泉太郎、服部潤次郎到着 | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 8月11日 | 16 | 乗馬姿を写真撮影 | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 9月1日 | 16 | ビアリッツ着、離宮でナポレオン一家に暇乞い | ||
| 1868年 | 慶応4年 | 9月4日 | 16 | 夜、ペリュ-ズ号でマルセイユを出帆 | ||
| 1868年 | 明治元年 | 9月8日 | 32 | 明治と改元 | ||
| 1868年 | 明治元年 | 11月3日 | 16 | 夕刻 神奈川上陸 | ||
| 1869年 | 明治元年 | 11月23日 | 17 | 天皇に拝謁、外国の事情を説明する*5 | ||
| 1869年 | 明治元年 | 11月24日 | 17 | 昭武に箱館賊徒追討を命じる事を決定*4 | ||
| 1869年 | 明治元年 | 11月25日 | 17 | 水戸藩襲封(第一一代藩主) | ||
| 1868年 | 明治元年 | - | 32 | 亀谷徳二郎、同とよ父子、京都より長崎に帰り木下町に写真館を開く*3 | ||
| 1868年 | 明治元年 | - | 32 | 船橋鍬次郎に「京都の旅舎における自像」、「旅館内厩」、「愛馬飛電」、「二条城内」、「二条城本丸」(鶏卵紙四ツ切)を撮影させる*3 | ||
| 1868年 | 明治元年 | - | 33 | 静岡在住の慶喜、船橋鍬次郎について写真術を研究する*3 | ||
| 1868年 | 明治元年 | - | 32 | 明石博高、将軍慶喜に乞いてオランダより写真器械を購め、わが国初の大板撮影を行い印画を献上する*3 | ||
| 1869年 | 明治2年 | 4月15日 | 17 | 水戸藩兵士二百人、箱館賊徒追討のため江差へ向かう | ||
| 1869年 | 明治2年 | 5月 | 33 | 徳田孝吉、朝敵として幽閉中の松本良順に写真術を学ぶ*3 | ||
| 1869年 | 明治2年 | 6月17日 | 17 | 版籍奉還を許され、水戸知事に任命される*4 | ||
| 1869年 | 明治2年 | 8月17日 | 17 | 水戸藩に天塩国の苫前・天塩・上川・中川・麟嶋の五郡の開拓許可おりる*4 | ||
| 1869年 | 明治2年 | 9月14日 | 17 | 参朝、箱館追討の軍功をもって三千五百石の永世下賜の行賞を受ける*4 | ||
| 1869年 | 明治2年 | 9月28日 | 33 | 謹慎を解かれる |
年表の作成には『徳川慶喜公伝』史料編(続日本史籍協会叢書・東京大学出版会)、『徳川慶喜のすべて』(新人物往来社)、『渋沢栄一滞仏日記』(続日本史籍協会叢書・東京大学出版会)、『徳川昭武』(中公新書)、『新稿 一橋徳川日記』(続群書類従完成会)などを参照し、自記の*1、*2、*7の資料から徳川慶喜と昭武に関する写真関係記事などを付加した。なお、年表中の注記は次の通り。また、徳川昭武渡欧時の年月日は陰暦によった。
*1『徳川慶喜家家扶日記』(未公刊・個人蔵)、*2『松戸御別邸日録』(未公刊・『松戸徳川家資料目録』第二集参照)、*3『日本写真史年表』(講談社)、*4『水戸藩資料』(吉川弘文館)、*5『明治天皇紀』(吉川弘文館)、*6『御日記』(未公刊・徳川昭武の第一次渡欧時の自筆日記・『松戸徳川家資料目録』第一集参照)、*7『(戸定)備忘録』(未公刊・徳川昭武自筆の手控え・『松戸徳川家資料目録』第一集参照)