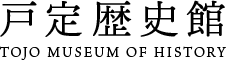展示情報
年間展示
開催中
通常展「お初にお目にかかります ―大集合!初めて展示される資料たち―」
●展示内容
戸定歴史館では開館以来、徳川昭武とその一族に関わる資料を収集し、調査・研究を進めてきました。その成果は、これまでに開催した展覧会や作成した図録などにて発表しています。しかし、調査・研究によって歴史的な価値が認められながらも、展覧会でお披露目できていない資料も多くあります。また、新たに収集した貴重な資料も少なくありません。本展覧会では、これらの資料に焦点をあて、初めて展示される資料を中心にご紹介します。
●会期
令和8年2月14日(土曜)から令和8年5月31日(日曜)
前期展示 令和8年2月14日(土曜)から令和8年4月12日(日曜)
後期展示 令和8年4月14日(火曜)から令和8年5月31日(日曜)
●会期中の休館日
2月:16日(月曜)、24日(火曜)
3月:2日、9日、16日、23日、30日(いずれも月曜)
4月:6日、13日、20日、27日(いずれも月曜)
5月:7日(木曜)、11日(月曜)、18日(月曜)、25日(月曜)
●章立て
松戸徳川家資料
水戸徳川家11代当主・徳川昭武は、明治15年(1882)に松戸の戸定に邸宅(戸定邸)を建てはじめます。明治17年(1884)に落成し、前年に隠居の立場となっていた昭武の生活拠点となりました。昭武は明治43年(1910)に亡くなるまで、趣味の写真撮影や狩猟、釣り、陶芸などを楽しみながら暮らしました。
松戸徳川家は、明治25年(1892)5月3日、昭武2男の武定が水戸徳川家より分家し、昭武の勲功により子爵を授けられて成立しました。
昭武の死後、武定は明治44年(1911)9月1日に戸定邸を松戸徳川家の本邸に定め、のちに相続で自身の名義とします。また、昭武が残した資料も受け継ぎ、整理に尽力しました。現代まで松戸徳川家資料が伝わったのは、武定の功績が大きく、徳川昭武の生涯を分析する基礎資料となっています。加えて、松戸徳川家資料には、武定をはじめとする一族に関わる資料も多く伝来しており、当館では同資料を継続的に研究しています。
津山松平家分家
明治21年(1888)11月1日、津山松平家11代当主・松平齊民8男の齊は、津山松平家より分家し、齊民の勲功により男爵を授けられました。ここに、津山松平家分家が成立します。
齊は、明治28年(1895)12月に徳川慶喜7女の浪子と結婚しました。浪子は、明治30年(1897)2月10日に長男・齊光を出産、明治37年(1904)5月20日付けで齊光が津山松平家分家2代当主となります。齊光は、大正9年(1920)11月14日、徳川昭武の3女・直子と結婚しました。
令和6年(2024)、当館は津山松平家分家より同家の実態や徳川慶喜・昭武、戸定邸について新たな事実を発見し得る貴重な資料の寄贈を受けました。
須見裕旧蔵資料
徳川昭武の4女・温子は、大正10年(1921)4月16日、丸亀京極家11代当主・高修と結婚し、1男4女を授かりました。その3女・千代子は、須見裕と結婚します。
陸軍大尉であった須見裕は戦後、一級建築士となり、歴史研究にも心血を注ぎました。昭和59年(1984)には、中央公論社より『徳川昭武 万博殿様一代記』を出版します。松戸徳川家2代当主・博武の協力を受けながら、「一族の長老」一橋徳川家12代当主・宗敬の許しを得て研究・執筆にあたりました。徳川昭武研究のパイオニアと言っても過言ではないでしょう。須見裕が昭武研究を進める中で収集した資料が須見家に伝わり、令和7年(2025)に当館へ寄贈されました。
毛利政子旧蔵資料
明治18年(1885)8月6日、昭武の2女・政子は戸定邸で誕生しました。政子は、明治39年(1906)6月17日に長府毛利家16代当主・元雄と結婚します。
その後、昭武と政子は手紙のやり取りを続けます。政子の手元には、昭武から送られた手紙17通が残りました。中には「大乱筆御一覧後、速かに御火中御火中御火中」(大乱筆にて記した手紙なので、一通りご覧になった後すぐに焼却してください)と「御火中」を3度記すほど処分の念を押した手紙もあります。しかし、政子は大切に保管していたようで、現在まで伝わりました。これら毛利政子宛徳川昭武書状は姪・徳川宗子(武定長女、博武夫人)の手を経て平成2年(1990)に松戸市へ寄贈されました。
●ギャラリートーク
展示の見どころを学芸員が解説します。
日時
令和8年2月28日(土曜)、4月25日(土曜) 各13時30分から30分程度
会場
戸定歴史館展示室
申し込み
不要
費用
戸定歴史館入館料
●入館料
区分 | 個人 | 団体(20人以上) |
| 一般 | 150円 | 120円 |
| 高校生・大学生 | 100円 | 80円 |
区分 | 個人 | 団体(20人以上) |
| 一般 | 250円 | 200円 |
| 高校生・大学生 | 100円 | 80円 |
区分 | 個人 | 団体(20人以上) |
| 一般 | 320円 | 250円 |
| 高校生・大学生 | 160円 | 120円 |
次の方は無料で入館できます
・身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人とその介護者1名
(手帳をご提示ください)
・中学生以下
各展覧会の内容
通常展 「暦と調度ー春から夏の戸定邸」
戸定歴史館が所蔵する数千点の歴史資料のなかから、春から夏にかけての調度品を選んで展示します。展覧会が始まる3月下旬のサクラの開花シーズンから、風薫る5月下旬まで、戸定が丘の自然とあわせて季節を感じられる展覧会です。
会期
令和7年3月20日(木曜・祝日)から6月6日(金曜)
連携特別展 「まつど×とくがわ― 昭武・武定の生きた明治・大正・昭和」
水戸徳川家11代当主の徳川昭武は、隠居後、松戸の戸定が丘に私邸(戸定邸)を建設し、明治17年(1884)に移り住みます。昭武・武定(昭武2男、松戸徳川家初代当主)をはじめとする戸定邸の人びとは、周辺地域と関わりながら、新しい環境での生活を営みました。
本展では、戸定歴史館・松戸市立博物館の2館が連携し、それぞれの所蔵資料と視点で、戸定邸を取り巻く松戸市域の明治・大正・昭和を見つめ直します。小学生を中心に、子どもから大人まで「まつど」に親しんでいただける展覧会です。また、スタンプラリーや絵本の読み聞かせなどの関連イベントも予定しています。
会期
令和7年7月12日(土曜)から8月31日(日曜)
通常展 「万博・博 ―1867パリから、はじまる―」
徳川昭武が日本の代表として参加した1867年パリ万国博覧会は、日本の国際デビューのきっかけとなりました。昭武と共に渡欧した渋沢栄一ら万博経験者は、明治維新後の近代日本を牽引する役割を果たしました。今回の展覧会では、昭武と、彼の教育責任者としてパリ万博に随行し、後に美術・博覧会行政の中心となった山高信離の視点から、1867年から1900年までの10回におよぶ万博を紹介します。
会期
令和7年10月4日(土曜)から令和8年1月12日(月曜・祝日)
通常展 「お初にお目にかかります ―大集合!初めて展示される資料たち―」
戸定歴史館では開館以来、徳川昭武とその一族に関わる資料を収集し、調査・研究を進めてきました。その成果は、これまでに開催した展覧会や作成した図録などにて発表しています。しかし、調査・研究によって歴史的な価値が認められながらも、展覧会でお披露目できていない資料も多くあります。また、新たに収集した貴重な資料も少なくありません。本展覧会では、これらの資料に焦点をあて、初めて展示される資料を中心にご紹介します。
会期
令和8年2月14日(土曜)から5月31日(日曜)
- 令和5年度の展示・イベント
- 令和4年度の展示・イベント
- 令和3年度の展示・イベント
- 令和2年度の展示・イベント
- 平成31年度の展示・イベント
- 平成30年度の展示・イベント
- 平成29年度の展示・イベント
- 平成28年度の展示・イベント
- 平成27年度の展示・イベント
- 平成26年度の展示・イベント
- 平成25年度の展示・イベント
- 平成24年度以前の戸定のイベント
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。