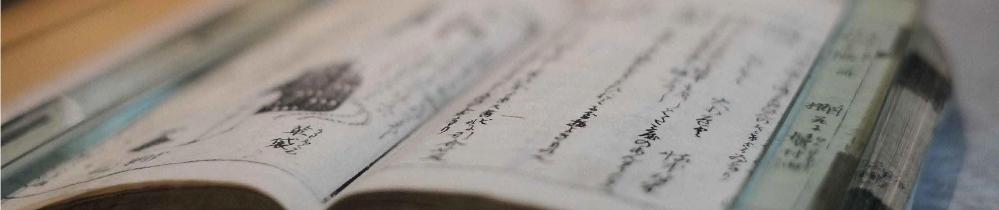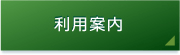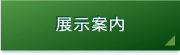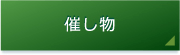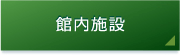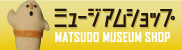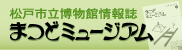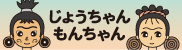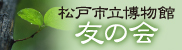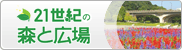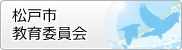館長室から
松戸市立博物館長 渡辺 尚志
挨拶
2022年4月から館長に就任しました、渡辺尚志と申します。専門は日本近世史(江戸時代史)で、江戸時代の村と農民の歴史についてずっと研究してきました。
私は約30年前から松戸市に住んでいますので、松戸市の近世についても少しずつ研究しています。具体的な成果としては、幸谷村(現在の新松戸駅周辺)を取り上げた『殿様が三人いた村』(崙書房出版、2017年、現在は絶版)、『言いなりにならない江戸の百姓たち』(文学通信、2021年)を刊行しました。また、論文集『近世の村と百姓』(勉誠出版、2021年)のなかにも、幸谷村を対象とした論文を収めています。松戸市域以外を扱った最近の出版物としては、2022年4月に『武士に「もの言う」百姓たち』が草思社文庫から再刊されました(初版は2012年)。これからもさらに松戸市域の歴史研究に力を入れ、その成果をわかりやすく皆様にお伝えしていきたいと思います。
経歴
1957年、東京都生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得退学。博士(文学)。一橋大学名誉教授。専門は日本近世史・村落史。
著書
- 『松戸の江戸時代を知る(1) 小金町と周辺の村々』(たけしま出版、2023年)
- 『松戸の江戸時代を知る(2) 城跡の村の江戸時代』(たけしま出版、2023年)
- 『松戸の江戸時代を知る(3) 川と向き合う江戸時代』(たけしま出版、2024年)
- 『松戸の江戸時代を知る(4) 増補新版 殿様が三人いた村』(たけしま出版、2024年)
- 『松戸の江戸時代を知る(5) 江戸時代の松戸河岸と鮮魚輸送─河岸問屋・青木源内家を中心に─』(たけしま出版、2025年)
- 『松戸の江戸時代を知る(6) 『江戸時代の小金牧と金ケ作村』(たけしま出版、2025年)
- 『百姓たちの江戸時代』(ちくまプリマー新書、2009年)
- 『百姓の力 江戸時代から見える日本』(角川ソフィア文庫、2015年)
- 『百姓たちの幕末維新』(草思社文庫、2017年)
- 『江戸・明治 百姓たちの山争い裁判』(草思社文庫、2021年)
- 『海に生きた百姓たち』(草思社文庫、2022年)
- 『百姓たちの水資源戦争 江戸時代の水争いを追う』(草思社文庫、2022年)
- 『武士に「もの言う」百姓たち 裁判でよむ江戸時代』(草思社文庫、2022年)
テレビ出演
- NHK BS「英雄たちの選択」(BS4K:2024年11月7日 20時から、BS:2024年11月11日 21時から)
最新!一茶は馬橋で俳諧(はいかい)を覚えた? 小林一茶と松戸(2) (2025年11月3日)
前回は、小林一茶の生涯について述べました。今回からは、一茶と松戸の関わりについて述べていきます。
一茶は15歳のとき江戸に出ましたが、その後の10年間どこで何をしていたかわかりません。ところが、その間、彼が馬橋(まばし)村(現松戸市)の商家に住み込みで働いていたとする説(一茶の馬橋奉公説)があるのです。その商家とは、大川家です。同家は、当時、油問屋を営んでいました。アブラナの実から照明用の油を搾(しぼ)り、それを各地に売り出していたのです。当時の大川家当主の平右衛門(へいえもん)は、立砂(りゅうさ)という俳号をもつ俳人でもありました。以下、一茶の馬橋奉公説を御紹介しましょう。
現松戸市域の郷土史を研究された青木源内氏は、論文「馬橋の俳人大川立砂と小林一茶との因縁について」(『松戸史談』11号)で、次のように述べています。
立砂の屋敷は中宿といわれた馬橋村の中心部に位置し、彼の先代のときに大川吉右衛門(きちえもん)家から分家してできた家でした。一茶は、立砂のもとに住み込んで働いているうちに、俳諧を覚えました。
百姓一揆研究や近世庶民文化史の分野で大きな業績を残した青木美智男氏は、『小林一茶』(山川出版社)のなかで、次のように述べています。
立砂は、当時江戸の本所・深川から房総にかけて広く勢力を伸ばしていた葛飾派(かつしかは)の遊俳(ゆうはい)で、弥太郎(やたろう、一茶の幼名)もそこに身をよせ俳諧に親しみだしたとみるのが、立砂とのその後の関係をみれば妥当な推測であろう。(『小林一茶』三六ページ)
また、青木美智男氏は、『小林一茶』(岩波書店〈岩波新書〉)でも、同様のことを述べています。
奉公先の一つだった下総国(しもうさのくに)馬橋の油商人大川立砂の家で俳諧のいろはを教えられたことが役に立った。立砂は、当時江戸の本所深川から房総にかけて広く勢力を伸ばしていた葛飾派の俳諧師で、弥太郎もその縁で葛飾派の誰かの家に身を寄せ俳諧に親しみだしたというのが通説である。(『小林一茶』五〇ページ)
このように、青木源内・青木美智男両氏は、一茶が10代後半から20代前半頃に、馬橋の大川家に奉公していた時期があるといっています。そればかりか、そのとき立砂の影響で俳諧(俳句)に親しむようになったというのです。そうだとすると、俳人一茶は馬橋で誕生したことになります。しかし、残念ながら、それを立証する確実な史料は今日まで見つかっていません。もし、今後見つかれば大発見でしょう。事実かどうかはさておき、馬橋で暮らす青年一茶の姿を想像してみるのも楽しいですね。