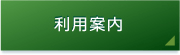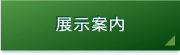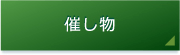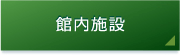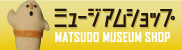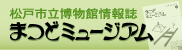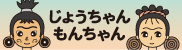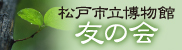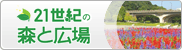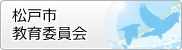松戸市立博物館の学芸員紹介
富澤 達三(とみざわ たつぞう)
専門分野
江戸時代の日本について研究しています。松戸に残る古文書を整理し、読み解くことで、江戸時代の松戸を具体的に調べています。また、図像から江戸時代を探る研究にも力をいれています。
どんな仕事をしているか
博物館で保管している古文書を中心に整理し、読み解いています。さらに、市内旧家に残されている古文書の調査も行っています。そのほか、学芸員講演会やパートナー講座で松戸の江戸時代について発信しています。
過去に担当した代表的な展示
- 館蔵資料展「まつどの江戸時代」(平成30年度)
- 企画展「松戸と徳川将軍の御鹿狩」(令和2年度)
- 館蔵資料展「古文書をみる絵図をよむ」(令和4年度)
- 館蔵資料展「古文書からさぐる大谷口の村」(令和6年度)
学芸員の活動
- 学芸員講演会「庚甲講とはなんだろう」(令和5年度)
- 学芸員講演会「古文書からさぐる大谷口村-石造物をさらに考える」(令和6年度)
松戸市立博物館のココがおすすめ!
「松戸河岸の模型」。江戸川を船で下り、江戸へさまざまなモノを運ぶ中継地として賑わった松戸河岸が、とても詳しく再現されています。ほかにも「御鹿狩シアター」は、今の五香公園ちかくで行われた徳川将軍の御鹿狩を、音響と細かい人形の動きで解説しています。
松戸の歴史解説(広報まつど 令和2年6月15日号掲載)
当館学芸員がそれぞれの専門分野の歴史解説をしています!
松戸と徳川将軍の御鹿狩
西村 広経(にしむら ひろつね)
専門分野
先史考古学、とくに東日本の縄文時代を中心に研究しています。狩猟採集民が自然環境にどのように適応したのか、その中でどのように複雑な社会を形成していったのか、といった問題に取り組んでいます。最近は北海道・東北・関東の土器を見比べながら、地域間の関係の変化を探っています。
過去に担当した代表的な展示
- 館蔵資料展「イランの技とデザイン:奥井コレクション展」(令和4年度)
- 企画展「異形土器 縄文時代のふしぎなうつわ」(令和6年度)
学芸員の活動
- 口頭発表「東日本の縄文後期中葉土器群と異形土器」(企画展記念シンポジウム、令和6年10月)
- 講演会講師「縄文後期の異形土器」(松戸市立博物館、令和6年10月)
松戸市立博物館のココがおすすめ!
縄文の森。地中に残されていた花粉や発掘調査でみつかった動植物などのデータから縄文時代後期(約4000年前)の森を復元しています。森の資源を巧みに利用した暮らしぶりを体感してみてください。
松戸の歴史解説(広報まつど 令和2年8月15日号掲載)
当館学芸員がそれぞれの専門分野の歴史解説をしています!
貝の花の不思議な土器
米村 創(よねむら そう)
専門分野
民俗学 年中行事や祭礼、人生儀礼、民間信仰などを通し、共通して見えてくる「人の精神」について研究しています。
どんな仕事をしているか
令和6年度は、こども探検教室「親もたのしむ 米づくりと展示づくり―小学生学芸員になろう―(全9回)」に関わり、参加者の親子と一緒に田んぼで稲作を行いました。
松戸市立博物館のココがおすすめ!
プレイルームでは、糸車による糸紡ぎが行えたり、アンギン(編布)製作の体験ができたりします。昔の人の生活用品作りについておもしろく学べる場所です。
林 幸太郎(はやし こうたろう)
専門分野
日本の近現代史を研究しています。とくに、明治維新期に注目し、明治初期の小金原開墾事業など、「御一新」に向き合った市域の人びとの姿を探っています。また、近代社会における旧大名家と旧家臣団・旧領民の結びつきについても関心があります。
どんな仕事をしているか
松戸市域の歴史を伝える文字資料(公文書、個人宅の文書、雑誌・新聞など)の保存と調査研究に取り組んでいます。また、皆様がより活用しやすくなるように、広報課旧蔵写真をはじめとする写真・映像資料の収集と公開準備も進めています。
過去に担当した代表的な展示
- 企画展「あの日の“まつど”―写真でふりかえる150年―」(令和5年度/共同担当)
- 館蔵資料展「古文書からさぐる大谷口の村」(令和6年度/共同担当)
学芸員の活動
- 学芸員講演会「写真と文書でふりかえる“まつど”―松戸町・坂川普通水利組合・陸軍工兵学校―」(松戸市立博物館、令和5年度)
- 学芸員講演会「小金原開墾事業と開墾会社―五香六実を拓いた人々(2)―」(松戸市立博物館、令和6年度)
- 資料紹介「松戸市立博物館所蔵「大谷口村大熊家文書」―大熊伊兵衛と「御進発御供」―」(『松戸市立博物館紀要』第32号)
松戸市立博物館のココがおすすめ!
主題展示室「二十世紀梨の誕生」。松戸市指定文化財である「二十世紀梨の原木」と迫力のある梨の樹が迎えてくれます。二十世紀梨をはじめとするニホンナシの歴史や栽培の映像など、今なお松戸の特産物である梨を深く知るきっかけになると思います。梨園へ遊びに行く際には、ぜひお立ち寄りください。
中山 文人(なかやま ふみと)
専門分野
日本の中世(平安時代の後半から戦国時代)を古文書・古記録といった文字資料をおもな素材に使って研究します。「こんな博物館もアリだね」って形や動かし方を考える博物館学もやっています。
どんな仕事をしているか
展示会を開いたり、いろいろな文章を書いたり、皆さんの前でお話ししたり・・・。それぞれを関連させながら、仕事を進めるように意識しています
過去に担当した代表的な展示
- 企画展「あの日の“まつど”―写真でふりかえる150年―」(令和5年度/共同担当)
- 館蔵資料展「小金城と根木内城+郷土玩具展リターンズ」(令和3年度)
- 企画展「本土寺と戦国の社会」(平成29年度)
学芸員の活動
- 講座講師「戦国時代の松戸市域と東葛のようす」(松戸市パートナー講座/令和5年度)
- 講座講師「戦国時代の小金と寺院」(松戸市パートナー講座/令和6年度)
- 学芸員講演会「松戸の『中世を増やす』試み」(松戸市立博物館、令和6年度)
- 明治大学学芸員養成課程特別講義「歴史系地域博物館の学芸員の活動」(令和5・6年度)
松戸市立博物館のココがおすすめ!
広い縄文時代の展示や野外の竪穴住居と常盤平団地の復元模型。昔と今を見比べるとより面白くなると思います。それから、松戸デジタルミュージアム、ご来館の前後に、展示室でもご覧になれます。
松戸の歴史解説(広報まつど 令和2年5月1日号掲載)
当館学芸員がそれぞれの専門分野の歴史解説をしています!
小金城と根木内城
青木 俊也(あおき としや)
専門分野
民俗学 特に人の一生に関わる葬送儀礼について、松戸市域の大半が農村だった1950年代から現在に至る変化について研究しています。
博物館展示論 各地の歴史博物館における昭和30年代を中心とした生活展示がつくられてきた意味について研究しています。
どんな仕事をしているか
本年度は、館蔵資料展「誕生・結婚・死の儀礼」の準備に取り組んでいます。
過去に担当した代表展示
- 企画展「こどもミュージアム」(令和元年度)
- 企画展「戦後松戸の生活革新」(平成12年度)
学芸員の活動
- 神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科非常勤講師「博物館歴史資料学特論」(令和3年度)
- 編集:松戸市立博物館報告書7『森の住宅都市常盤平団地の生活史1960-2022』(令和4年度)
- 編集:松戸市立博物館報告書8『「こどもミュージアム」展示開発に向けた制作途中報告書」(令和5年度)
松戸市立博物館のココがおすすめ!
常設展示室では、2019年で60周年を迎えた常盤平団地における1962年の生活が展示してあります。皆さんの生活とどのようなところが違い、どのようなところが同じか、考えてみると面白いと思います。
松戸の歴史解説(広報まつど 令和2年6月1日号掲載)
当館学芸員がそれぞれの専門分野の歴史解説をしています!
常盤平団地60年の生活史に向けて