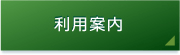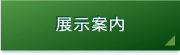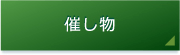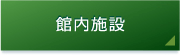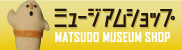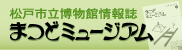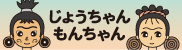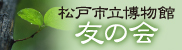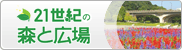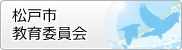市立博物館学芸員による松戸の歴史解説「小野遺跡ー古代の松戸を知る遺跡ー」
小野遺跡は胡録台にある奈良・平安時代の遺跡です。1992(平成4年)の発掘調査で、非常に注目された2つの発見がありました。
一つ目は、古代の役人の身分を表す腰帯(ベルト)に付けられた帯金具です。この帯金具は官位が六位以下の役人が用いたものでした。この時代の遺跡から1、2点発見されることはありますが、一帯分が発見されることは大変珍しく、現在でも小野遺跡を含め、全国で数例しかありません。市川市に下総国府(市川市国府台にあった国の役所)があったことから、おそらくそこで働く役人が身に着けていたものと思われます。帯金具と一緒に金属加工に関係する工具も発見されました。そのため小野遺跡は腰帯の補修などを行なった場所だったと考えられます。
二つ目は、「石世」と墨で書かれた土器(墨書土器)です。石世は、「いわせ」と読むことができます。小野遺跡周辺は1889年(明治22年)までは「岩瀬村」と呼ばれていたので、この地名の起源が古代(約1,200年前)までさかのぼる可能性がある、貴重な発見でした。
ここで紹介した帯金具と墨書土器は博物館の総合展示室で見ることができます。

帯金具

墨書土器「岩世」
地図
小野遺跡(第一地点)