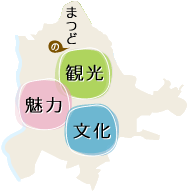水とみどりと歴史の回廊マップ(松戸地区)~歴史・Part2~
更新日:2013年11月25日
1.原田米屋
![]()
旧水戸街道沿いにある米屋で、明治末に建築されました。軒を出桁造とし1階正面をシトミ戸(上げ下げの板戸)とするなど幕末以来の2階建商家の形式を踏襲しています。骨組の木も太く、丈の高いシトミ梁を通し重厚な建て構えをしています。
原田米屋
2.旧松戸宿本陣跡
![]()
幕府が水戸街道を整備すると、松戸と小金は宿場町として繁栄します。現在の松戸郵便局の辺りには、大名などの宿泊施設である本陣や脇本陣がありました。旧本陣は幕末の火災で焼失し、直後に再建されましたが平成16年に取り壊されました。
旧松戸宿本陣跡
3.御料傍示杭跡
![]()
江戸時代、水戸街道を船でつなぐ渡しは、重要な関門であり、金町側に関所が設けられていました。この通りは、「渡船場道」と呼ばれ、両側に旅籠屋や船持・船乗・魚類商が軒を連ね、「松戸宿の出入口を示した傍示杭」が立てられていました。
平成7年に「是より御料松戸宿」の碑が立てられました。
御料傍示杭跡
4.戸定邸
![]()
松戸市街を一望出来る高台にあります。「戸定」とは古く中世の城郭に起源を持つ地名です。松戸市は江戸幕府の直轄地で、水戸藩ともゆかりの深い土地でした。戸定邸は、最後の水戸藩主であった徳川昭武(あきたけ)(15代将軍慶喜の弟1853年~1910年)によって明治17年に建てられ、昭和26年に徳川家から松戸市に寄贈されました。芝生を使い、洋風を取り入れた庭園は千葉県の名勝に指定され、建物は明治前期の上流住宅の姿をよく伝えるものとして平成18年に国の重要文化財に指定されました。
戸定邸
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。