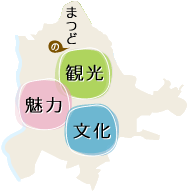水とみどりと歴史の回廊マップ(上本郷地区)~Part2~
更新日:2013年11月25日
6.ゆるぎの松 ★上本郷の七不思議(5)
![]()
昔、上本郷の高台に枝ぶりの良い大きな松がありました。
ある時、水戸黄門様の目に留まり、松の幹を撫でたところ、松はゆらゆらと揺れたそうです。それ以来「ゆるぎの松」と呼ばれるようになりました。しかし、この松は大正末期に枯れてしまったそうです。

ゆるぎの松
7.明治神社(めいじじんじゃ)
![]()
現在の祭神は、国常立命(くにのとこたちのみこと)ですが、神仏混合禁止によって明治5年に社名を改める前は、「妙見社」と称し、戦の神の妙見菩薩を祀っていました。
妙見菩薩は、北極星や北斗七星を神格化した千葉氏の守護神です。
【千葉氏と妙見神】
千葉の地を治めた千葉氏の祖・平良文は、戦のたびごとに妙見尊に祈願して御加護をいただき、常に大勝利を収めていたので、以後、千葉家では代々一門の守護神として熱烈な信仰をささげ、移り住んだ全国各地の領地に妙見神を祀りました。

明治神社(めいじじんじゃ)
官女の化けもの ★上本郷の七不思議(6)
![]()
昔、雷(いかずち)神社が祀られていた「いかずち山」に、夜な夜な真っ赤な袴をはいた官女の化けものが現れて人を驚かせたそうです。
この「いかずち山」は龍善寺の付近だったといわれていますが、はっきりとは分かっていません。
なお、現在明治神社の社殿左側に奉納されている雷電宮ときざまれた石が雷神社のものではないかと言われています。

8.二ツ井戸 ★上本郷の七不思議(7)
![]()
もとはここに、つるべ井戸が二つ並んでいました。不思議なことに、どちらか一方の井戸が澄んでいると隣の井戸が濁っていたそうです。昔からこの地区では、「二ツ井戸があるので他に井戸を掘ってはいけない。」と言われてきたそうです。

二ツ井戸
9.中根城(小金城)跡 安房須神社
「鎌倉大草紙」に記載のある鎌倉時代中期に千葉頼胤(よりたね)が在城した小金城が、ここにあった中根城ではないかと言われています。
今日では、ほとんどが住宅地になっていますが、妙見神社から安房須神社辺りまでが城郭(じょうかく)だったと推測され、安房須神社付近に城郭の遺構らしきものをわずかに見ることができます。

10.妙見神社
妙見神社の祭神は、神仏混合禁止によって国常立命に改められましたが、それ以前は、千葉氏の守護神である妙見菩薩でした。

【中根妙見神社伝説】
九州千葉氏の祖であった千葉胤貞(たねさだ)は、肥前国(佐賀県)にも所領があり、何回か肥前と下総を往復しますが、南北朝の混乱期で戦い疲れた胤貞が中根城へ戻ったところ、城が荒廃していたそうです。この城主の痛ましい姿を見た農民が傍らの松の枝を三本折り、憩いの場所を作ってあげました。そして、妙見神社は、その跡に建てられたものと伝えられています。
農民はそのとき「三枝松」の姓をもらい、明治の初め頃までの千葉妙見社祭礼の際の開扉は、馬橋の三枝松氏が行うようになったそうです。
11.首斬り地蔵
![]()
元治元年(1864年)のこと、水戸藩士の佐藤久太郎が佐幕派家老の市川三左衛門(いちかわさんざえもん)に与したことにより、尊皇派の水戸藩士に捕まり、下総本郷村で首を斬られてしまいました。村民は哀れに思い久太郎が斬られた場所にお地蔵様を建てて冥福を祈ったそうです。
やがてお地蔵様のあったあたりは、藪におおわれて長い間忘れられておりましたが、昭和9年の龍善寺建立の工事で偶然発見されました。

首斬り地蔵
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。