国民年金保険料の申請免除・学生納付特例・納付猶予、法定免除、産前産後期間免除、追納
更新日:2025年12月9日
国民年金の保険料には、経済的な理由や特例的な理由があり、納めることが困難なときに保険料が免除、猶予される制度や、学生については、在学中の保険料の納付が猶予される制度などが設けられています。
目次
申請免除制度(令和7年度:令和7年7月から令和8年6月)
免除には、全額免除・4分の3免除(4分の1納付)・半額免除(半額納付)・4分の1免除(4分の3納付)の4種類があり、本人・配偶者・世帯主の前年の所得額などに応じて日本年金機構で審査されます。
扶養人数 |
全額免除 |
4分の3免除 |
半額免除 |
4分の1免除 |
|---|---|---|---|---|
2人(例:配偶者・子) |
137万円 |
164万円 |
204万円 |
244万円 |
1人(例:配偶者) |
102万円 |
126万円 |
166万円 |
206万円 |
扶養なし |
67万円 |
88万円 |
128万円 |
168万円 |
(注釈1)一部免除の審査は、社会保険料控除額等を加味して行うため、表の金額と異なる場合があります。
免除が承認されると保険料を未納にしているよりも次のように有利になります
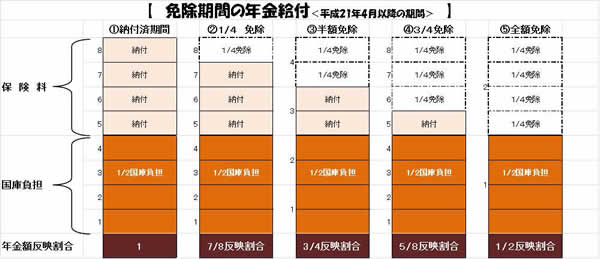
申請免除の対象となる人
- 前年の所得(収入)が少なく、保険料を納めることが困難な場合
- 障害者、寡婦またはひとり親であって、前年の所得が135万円以下の場合
- 1、2以外の特例的な理由による場合
特例的な理由とは
- 退職により保険料を納付することが困難と認められるとき
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、被害金額が財産価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
- 事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する総合支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき
ただし、これらの特例的な理由による場合は、申請の際にその事実を明らかにすることができる書類の添付が必要となります。
| 退職の場合 |
|
|---|---|
| 災害の場合 |
|
| 廃業の場合 |
|
申請に必要なもの
- 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)(注釈1)
- 上記の特例的な理由により申請する場合、必要とされる書類
(注釈1)現在、窓口における各種手続等においては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。マイナンバーカード実物をご持参くださいますようお願いいたします。
手続きについて(免除)
国保年金課国民年金班又は支所の窓口で各申請書を記載し、必要とされる書類を添えて提出してください。申請書は、国保年金課国民年金班又は支所の窓口にあります。
- 複数年度の申請を希望される場合は、年度ごとに申請書の提出が必要となります。
- 各申請書は申請書ダウンロードから、PDF形式で入手できます。
- 各申請書を記載し、必要とされる書類を添え、郵送でも申請することができます。
- 郵送で申請する場合は「〒271-8588 松戸市根本387の5 松戸市役所 国保年金課国民年金班」へ郵送してください。
納付猶予制度(令和7年度:令和7年7月から令和8年6月)
50歳未満の方で、本人および配偶者の前年所得が一定以下の人に対し、保険料の納付を猶予する制度です。
※世帯主の所得は関係せず、本人と配偶者の所得審査があります(扶養なしの場合、前年所得が67万円以下であること)。
承認されると保険料を未納にしているよりも次のように有利になります。
- 免除期間は老齢基礎年金、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます(老齢基礎年金の受給額には加算されません) 。
- 免除された保険料は10年以内であれば納めること(追納)ができます。
申請に必要なもの
- 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)(注釈1)
- 特例的な理由により申請する場合、必要とされる書類
(注釈1)現在、窓口における各種手続等においては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。マイナンバーカード実物をご持参くださいますようお願いいたします。
手続きについて(納付猶予)
国保年金課国民年金班又は支所の窓口で各申請書を記載し、必要とされる書類を添えて提出してください。申請書は、国保年金課国民年金班又は支所の窓口にあります。
- 複数年度の申請を希望される場合は、年度ごとに申請書の提出が必要となります。
- 各申請書は申請書ダウンロードから、PDF形式で入手できます。
- 各申請書を記載し、必要とされる書類を添え、郵送でも申請することができます。
- 郵送で申請する場合は「〒271-8588 松戸市根本387の5 松戸市役所 国保年金課国民年金班」へ郵送してください。
学生納付特例制度(令和7年度:令和7年4月から令和8年3月)
学生納付特例は、大学や専修学校の学生であって、本人の前年所得が一定以下の人に対し在学期間中、保険料の納付を猶予し、社会人になってから支払うことを期待して設けられた制度です。
※同居家族の所得は関係せず、学生本人だけの所得審査があります。(前年所得の目安は128万円以下であること)
学生納付特例制度が受けられる学校とは
- 大学、短期大学、大学院
- 専門学校、専修学校
- 各種学校、予備校
- 夜間部・定時制課程・通信制課程など
※学校法人の認可を受けていない各種学校、予備校、海外の学校の学生は学生納付特例の対象にはなりません。
承認されると保険料を未納にしているよりも次のように有利になります
- 免除期間は老齢基礎年金、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に算入されます。(老齢基礎年金の受給額には加算されません)
- 免除された保険料は10年以内であれば納めること(追納)ができます。
申請に必要なもの
- 学生証の写し(両面)または在学証明書(原本)
- 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)(注釈1)
- 特例的な理由により申請する場合、必要とされる書類
(注釈1)現在、窓口における各種手続等においては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。マイナンバーカード実物をご持参くださいますようお願いいたします。
手続きについて(学生納付特例)
国保年金課国民年金班又は支所の窓口で各申請書を記載し、必要とされる書類を添えて提出してください。申請書は、国保年金課国民年金班又は支所の窓口にあります。
- 複数年度の申請を希望される場合は、年度ごとに申請書の提出が必要となります。
- 各申請書は申請書ダウンロードから、PDF形式で入手できます。
- 各申請書を記載し、必要とされる書類を添え、郵送でも申請することができます。
- 郵送で申請する場合は「〒271-8588 松戸市根本387の5 松戸市役所 国保年金課国民年金班」へ郵送してください。
学生納付特例の承認を受けた方の申請方法が簡単になりました
初回の申請時に在学予定期間を記入している場合、その期間中、日本年金機構から4月以降に『学生納付特例申請書(ハガキ)』が送付されます。引き続き同じ学校に在学の方は、必要事項を記入して返送することにより新年度の申請ができます。学生証などは不要です。
ただし『学生納付特例申請書(ハガキ)』が届かなかった方や在学校を変更した方などは、従来どおりの申請が必要です。
さかのぼりの申請免除等の手続きについて(免除・納付猶予・学生納付特例)
各制度は申請日時点より、原則2年と1か月前まで遡って申請できます(平成26年4月年金機構強化法施行)
申請が遅れると、障害基礎年金等が受けられない場合があります。お早めに手続きをしてください。
申請年度 |
免除、納付猶予申請が可能な期間 |
審査の対象となる所得 |
|---|---|---|
令和4年度(注釈1) |
令和5年6月 | 令和3年中の所得 |
| 令和5年度 | 令和5年7月から令和6年6月 | 令和4年中の所得 |
| 令和6年度 | 令和6年7月から令和7年6月 | 令和5年中の所得 |
| 令和7年度 | 令和7年7月から令和8年6月 | 令和6年中の所得 |
(注釈1)令和4年度分については、令和7年7月31日までに申請が必要です。
| 申請年度 | 学生納付特例の申請が可能な期間 | 審査の対象となる所得 |
|---|---|---|
| 令和4年度(注釈2) | 令和5年3月 | 令和3年中の所得 |
| 令和5年度 | 令和5年4月から令和6年3月 | 令和4年中の所得 |
| 令和6年度 | 令和6年4月から令和7年3月 | 令和5年中の所得 |
| 令和7年度 | 令和7年4月から令和8年3月 |
令和6年中の所得 |
(注釈2)令和4年度については、令和7年4月30日までに申請が必要です。
免除・納付猶予・学生納付特例の審査結果について
承認結果について
申請後、日本年金機構からおおむね2から3カ月後に審査結果が送付されます。それまでの間、保険料納付の催告状等が送付される場合がありますので予めご承知ください。
なお、審査結果(承認通知)で、4分の3免除、半額免除、4分の1免除が承認された場合は、あらためて、納めるべき額が記載された納付書が届きますので、納付をお願いします。(注釈3)
全額免除・納付猶予が承認されますと、保険料を納める必要がありませんので、お手元の納付書は不要となります。
(注釈3)納付しなければ年金額及び資格期間に反映されず「未納扱い」となり、障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されない場合がありますのでお気を付けください。
申請が却下になった場合
保険料の納付が必要です。納付書がない場合は、日本年金機構松戸年金事務所に連絡してください。
継続申請について(全額免除・納付猶予のみ)
免除・納付猶予等の申請時に継続審査を希望された方(注釈4)は、翌年6月までは免除期間となり、次年度も全額免除、納付猶予の継続審査対象として自動審査されます(承認されると次年度も引き続いて国民年金保険料が免除又は納付猶予されます)。
なお、継続申請の結果については、日本年金機構から送付されますが、却下された場合でも一部免除に該当する場合もありますので、ご希望の場合は再度申請をしてください。
(注釈4)特例認定区分(退職等)で全額免除、納付猶予が承認された場合や、一部免除の区分で承認された場合は、継続申請の対象とならず、翌年度以降も申請が必要となりますのでご注意ください。
法定免除(障害年金受給者・生活保護受給者など)
次の1から3のいずれかに該当する国民年金第1号被保険者の方は届出していただくことで、保険料の支払いが免除となります。(「法定免除」といいます)。
詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の法定免除制度)」(外部サイト)をご覧ください。
- 障害年金の1級または2級を受給している方
- 生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方
- 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養されている方
申請に必要なもの
- 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)(注釈1)
- 障害年金証書(障害年金受給者の場合)
- 生活保護受給証明書(生活保護受給者の場合)
(注釈1)現在、窓口における各種手続等においては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。マイナンバーカード実物をご持参くださいますようお願いいたします。
- 厚生労働省に認可されたハンセン病療養所が発行する、いつから入所されているのかが分かる証明書(ハンセン病で療養されている方の場合)
手続きについて(法定免除)
- 申請書を記載し、必要とされる書類を添えて提出してください。日本年金機構松戸年金事務所か国保年金課国民年金班での申請となります。
- 各申請書は 申請書ダウンロードから、PDF形式で入手できます。
- 必要とされる書類を添え、郵送でも申請することができます。
- 郵送で申請する場合は「〒271-8588 松戸市根本387の5 松戸市役所 国保年金課国民年金班」へ郵送してください。
注意事項
- 松戸市で住民登録を行っていない場合は、住民票の登録をしている管轄の年金事務所か市区町村窓口での手続きになります。
- 法定免除を受けていた方が、厚生年金に加入したり、厚生年金加入中の配偶者の扶養になった場合は、その時点で法定免除が終了となります。その後、再び、国民年金第1号被保険者となった場合、法定免除の事由に該当していれば、再度、法定免除の手続きが必要になります。
法定免除の審査結果について
申請後、日本年金機構からおおむね2から3カ月後に審査結果が送付されます。それまでの間、保険料納付の催告状等が送付される場合がありますので予めご承知ください。
産前産後期間免除制度
国民年金第1号被保険者(自営業者など)が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
詳細については、「日本年金機構(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)」(外部サイト)をご覧ください。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます
(出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産された方を含みます)。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができますので、ご希望の方は、国保年金課国民年金班へお問い合わせください。
承認されると保険料を未納にしているよりも次のように有利になります
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます(届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例、法定免除が承認されている場合でも、届出が可能です)。
免除の対象となる人
以下の2点に該当する人
- 松戸市に住民登録(住民票)がある人
- 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
(注意)産前産後期間が「国民年金第2号被保険者(厚生年金加者)」及び「国民年金第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)」の方は、申請対象ではございません。勤務先または配偶者の勤務先へお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)(注釈1)
- 母子健康手帳等の出産予定日が確認できるもの(出産日以降に届出を行う場合で被保険者と子が別世帯の場合は、国保年金課国民年金班へお問合せください)
(注釈1)現在、窓口における各種手続等においては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。マイナンバーカード実物をご持参くださいますようお願いいたします。
手続きについて(産前産後期間免除)
- 出産予定日の6か月前から申請可能です(出産後の手続き期限はありません)。
- 国保年金課国民年金班又は支所の窓口で各申請書を記載し、必要とされる書類を添えて提出してください。申請書は、国保年金課国民年金班又は支所の窓口にあります。
- 各申請書は 申請書ダウンロードから、PDF形式で入手できます。
- 必要とされる書類(母子手帳の場合は保護者氏名が記載されているページと出産予定日のページの写し)を添え、郵送でも申請することができます。
- 郵送で申請する場合は「〒271-8588 松戸市根本387の5 松戸市役所 国保年金課国民年金班」へ郵送してください。
申請書ダウンロード
![]() 国民年金保険料 学生納付特例申請書(日本年金機構ホームページ)
国民年金保険料 学生納付特例申請書(日本年金機構ホームページ)
![]() 国民年金保険料免除 免除・納付猶予申請書(日本年金機構ホームページ)
国民年金保険料免除 免除・納付猶予申請書(日本年金機構ホームページ)
![]() 国民年保険料免除理由該当・消滅届書(法定免除)(日本年金機構ホームページ)
国民年保険料免除理由該当・消滅届書(法定免除)(日本年金機構ホームページ)
追納制度
申請免除や学生納付特例、納付猶予が承認された期間は、老齢基礎年金の年金受給額が、通常に保険料を納めた場合よりも少なくなってしまいます。そこで、生活にゆとりができたときなどは本人の申出により、10年前までさかのぼって納めることができる「追納制度」があります。追納することにより受給する年金を、減額されずに保険料を納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。
詳細については、日本年金機構(外部サイト)のホームページをお確かめください。
追納に関する注意点
- 承認された期間のうち、古い期間からの納付となります。
- 承認された期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合には、承認を受けた当時の保険料に加算額がつきます。
- 口座振替や、クレジット払いはできません。納付書のみのお支払いとなります。
手続き
- 追納の申込は、松戸年金事務所(外部サイト)で行います。


