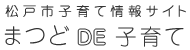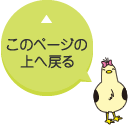子ども医療費(Q&A)
更新日:2025年3月10日
Q1 子ども医療費助成制度とは
A1
子どもの医療費を負担する保護者に医療費の一部を助成する制度です。
Q2 助成対象年齢は
A2
0歳から高校3年生相当年齢まで
Q3 保護者負担額は
A3
0歳から高校3年生相当年齢まで
- 通院1回200円・入院1日200円・調剤無料
- 市民税所得割非課税世帯は、無料です。患者自己負担額との差額を市が助成します。
※所得制限はありません。
令和5年8月1日から、自己負担上限額を設定しています
同一月に同一の医療機関を受診する場合、受給券を提示すると通院6回目、入院11日目以降の自己負担額(健康保険が適用される医療費に限る)が無料になります。
受給券が提示できなかった場合は、償還申請が必要です。
Q4 助成対象となる医療費は
A4
0歳から高校3年生相当年齢まで
- 健康保険適用の医療費(自己負担相当額)・食事療養費自己負担額が助成対象です。
- 健康保険適用の補装具も、助成対象です。
- 健康保険適用外の保険外併用療養費・予防接種・健康診断等は助成対象外です。
Q5 助成を受けるには
詳細は、子ども医療費助成制度(0歳から高校3年生相当年齢まで)をごらんください。
- 事前に子ども医療費受給券申請が必要です。
- 認定後に、受給券が送付され、医療機関等において、健康保険証と一緒に提示することで、助成が受けられます。なお、千葉県外の医療機関等の診療を受けられた場合は、受給券が使用できませんので、後日償還払いの申請が必要です。
Q6 休日に出生届を提出する場合は
A6
休日は子ども医療費助成制度の申請はできません。電子申請・郵送をご利用ください。
Q7 申請書の配付場所は
A7
市民課・各支所(市内8か所)・児童給付担当室で配付しております。
子ども医療費助成制度(0歳から高校3年生相当年齢まで)から電子申請・様式ダウンロードができます。
Q8 子ども医療費助成受給券の使用方法は
A8
医療機関(医科・歯科・調剤)受診時に、健康保険証とあわせて提示してください。
Q9 受給券の使用できる医療機関は
A9
千葉県内の医療機関(医科・歯科・調剤)で使用できます。千葉県外の医療機関では使えません。
Q10 受給券が使用できなかった場合は
A10
当ホームページの「子ども医療費助成における受給券が使用できなかった場合の申請(償還払い)」を参照のうえ、支払後2年以内に償還払いの申請をしてください。差額を助成します。
Q11 受給券の更新時期と更新方法は
A11
毎年、7月下旬に「8月1日から利用できる新しい受給券」を郵送します。更新にあたって、届出は必要ありません。書類の提出が必要な方には市より個別にご連絡します。
Q12 市内転居した場合は
A12
お子様の市内転居に係る届出は不要です。市民課・支所等で住所変更された日から 10日前後で、ご自宅へ自動的に変更後の受給券を郵送します。もし、変更後の受給券が届かない場合は、児童給付担当室にお問い合わせください。
必ず、事前に郵便局へ住所変更の手続きをしてください(変更の手続きをしない場合、受給券が届きません)。もし、未入居等の何らかの理由で、郵便で受け取りができない場合は、「 松戸市子ども医療費助成受給券 窓口受取・郵送日変更希望申請(PDF:190KB)」を 電子又は郵送・各窓口で行ってください。
Q13 市外へ転出した場合は
A13
転出日以降、受給券は使用できません。受給券は市へ返却するか、保護者の責任において破棄してください。
Q14 受給券交付後、市民税所得割非課税世帯になった場合
A14
税申告をされても自動的に反映されません。必ず変更届を提出してください。
申請の翌月1日より使用できる自己負担額0円の受給券を後日送付します。
Q15 受給券を医療機関に提示したが、200円以上の支払いがあった場合(主に通院)
A15
保険適用外のものは助成できません。領収書で「保険適用分」と判断できるもののみ助成されます。 (自費・保険適用外と表記されていませんか?)不明な場合は、医療機関へ確認してください。
Q16 受給券を医療機関に提示したが、200円以上の支払いがあった場合(主に入院)
A16
高額療養費に該当する可能性があります。高額療養費は加入している健康保険より支給されるものです。医療機関窓口で確認してください。高額療養費の支給に関することは、健康保険証の「保険者」へお問い合わせください。
なお、差額ベット代やおむつ代など保険適用外のものは助成できません。
Q17 高額療養費とは
A17
- 高額療養費とは、保険者が被保険者とその被扶養者に支払うべき法定給付です。
- 社会保険または国保組合に加入している方で、1ヶ月に〔80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〕で計算した自己負担限度額(高額療養費の自己負担限度額は所得に応じて、5区分に分かれており、前述の計算は一般所得の世帯の計算です)を超えた医療費が高額療養費となります。
- 高額療養費については、保険者に償還の申請をしてください。自己負担限度額については市で助成します。
- 医療機関にて受給券を提示して助成する場合は、高額療養費分は医療機関窓口で支払っていただき、保険者に償還の申請をしてください。なお、医療機関では「一般」の自己負担限度額で計算し、高額療養費分を助成していることが多いため、「上位所得者」の場合は、市へ償還払い申請をしてください。差額を助成します。
『限度額適用認定証』について
入院等で事前に高額の医療費がかかることがわかっている場合、保険者から『限度額適用認定証』の発行を受ければ、受給券・健康保険証と一緒に医療機関に提示することで、保護者の自己負担金のみの支払となります。(高額療養費についても医療機関での精算されます)
『限度額適用認定証』の発行はご加入の保険者にご確認ください。
【ご注意】償還払い申請前に、ご加入の健康保険組合等へ必ず申請手続きが必要な場合!
松戸市国民健康保険加入者以外の方で、同月・同医療機関で健康保険適用分の自己負担額が21,000円以上となる場合には、ご加入の健康保険組合等からの高額療養費支給(不支給)決定通知等の添付が必須となります。お手数ですが、償還払い申請前に領収書金額のご確認をしていただきますよう、お願い致します。
Q18 他の公費制度が適用される場合
A18
他の公費制度が優先されます。他の公費制度の自己負担金は、子ども医療費助成の対象となりますので、償還払い申請をしてください。(未熟児養育医療・身体障害児育成医療・小児慢性特定疾患等があります。適用の有無は医療機関に確認してください。)
Q19 保護者の変更があったとき(婚姻等による保護者の増減)
A19
変更届を提出してください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。