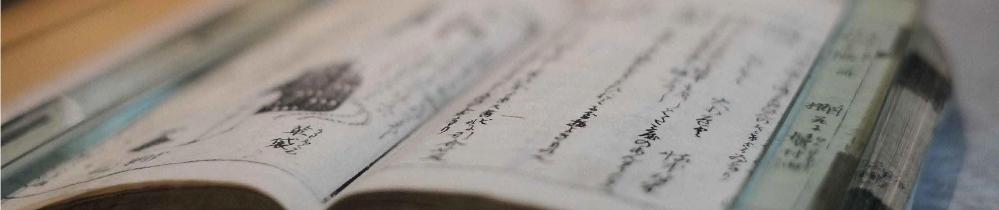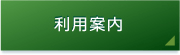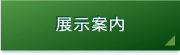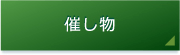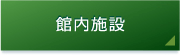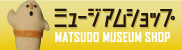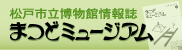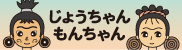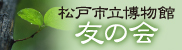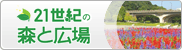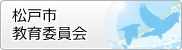館長室から
松戸市立博物館長 渡辺 尚志
挨拶
2022年4月から館長に就任しました、渡辺尚志と申します。専門は日本近世史(江戸時代史)で、江戸時代の村と農民の歴史についてずっと研究してきました。
私は約30年前から松戸市に住んでいますので、松戸市の近世についても少しずつ研究しています。具体的な成果としては、幸谷村(現在の新松戸駅周辺)を取り上げた『殿様が三人いた村』(崙書房出版、2017年、現在は絶版)、『言いなりにならない江戸の百姓たち』(文学通信、2021年)を刊行しました。また、論文集『近世の村と百姓』(勉誠出版、2021年)のなかにも、幸谷村を対象とした論文を収めています。松戸市域以外を扱った最近の出版物としては、2022年4月に『武士に「もの言う」百姓たち』が草思社文庫から再刊されました(初版は2012年)。これからもさらに松戸市域の歴史研究に力を入れ、その成果をわかりやすく皆様にお伝えしていきたいと思います。
経歴
1957年、東京都生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得退学。博士(文学)。一橋大学名誉教授。専門は日本近世史・村落史。
著書
- 『松戸の江戸時代を知る(1) 小金町と周辺の村々』(たけしま出版、2023年)
- 『松戸の江戸時代を知る(2) 城跡の村の江戸時代』(たけしま出版、2023年)
- 『松戸の江戸時代を知る(3) 川と向き合う江戸時代』(たけしま出版、2024年)
- 『松戸の江戸時代を知る(4) 増補新版 殿様が三人いた村』(たけしま出版、2024年)
- 『松戸の江戸時代を知る(5) 江戸時代の松戸河岸と鮮魚輸送─河岸問屋・青木源内家を中心に─』(たけしま出版、2025年)
- 『松戸の江戸時代を知る(6) 『江戸時代の小金牧と金ケ作村』(たけしま出版、2025年)
- 『百姓たちの江戸時代』(ちくまプリマー新書、2009年)
- 『百姓の力 江戸時代から見える日本』(角川ソフィア文庫、2015年)
- 『百姓たちの幕末維新』(草思社文庫、2017年)
- 『江戸・明治 百姓たちの山争い裁判』(草思社文庫、2021年)
- 『海に生きた百姓たち』(草思社文庫、2022年)
- 『百姓たちの水資源戦争 江戸時代の水争いを追う』(草思社文庫、2022年)
- 『武士に「もの言う」百姓たち 裁判でよむ江戸時代』(草思社文庫、2022年)
テレビ出演
- NHK BS「英雄たちの選択」(BS4K:2024年11月7日 20時から、BS:2024年11月11日 21時から)
最新!一茶の心の友・大川立砂 小林一茶と松戸(3) (2026年2月9日)
前回述べた、一茶の馬橋奉公説はいまだ確証がありませんが、一人前の俳諧師となった一茶が頻繁に現松戸市域を訪れたことは確かな事実です。そして、当地で一茶ともっとも深く交流したのが、馬橋村の大川立砂でした。
立砂は一茶よりかなり年長でしたので(立砂の生年が不明なので何歳年上かははっきりしません)、一茶から「爺」と慕われ、一茶のよき理解者であり、庇護者でもありました。一茶は、「立砂とは、私が俳諧の道に入ったときからの結びつきがあり、私と立砂との交わりはほかの人との交わりとは違う特別なものである」と記しています。
寛政一〇年(一七九八)一〇月に、立砂と一茶は真間の手児奈霊堂や真間寺(ともに現市川市)に遊び、次の句を詠んでいます。
夕暮の 頭巾へ拾ふ 紅葉哉 立砂
紅葉ゝや 爺はへし折 子はひろふ 一茶
手児奈霊堂とは万葉集にも載る名高い社で、古代の手児奈という悲劇の美女を祀る霊堂です。真間寺とは弘法寺のことで、紅葉の名所です。上記の句で、一茶は、立砂(爺)が紅葉の枝を折り、近所の子どもたちは落ち葉を拾っているさまを対照させて詠んでいます。
翌寛政一一年(一七九九)の三月に、一茶は甲斐国(現山梨県)から北陸への旅に出ましたが、そのとき立砂は竹ケ花村(現松戸市)まで一茶を見送りました。そのときに詠んだのが、次の句です。
今さらに 別ともなし 春がすみ(霞) 一茶
又の花見も命也けり 立砂
一茶が、春霞の立つもとで、今さらながら立砂とは別れたくないと、名残を惜しんでいるのに対して、立砂は、また来年一緒に花見ができるかどうかは運命しだいだと応えています。
ところが、同年の冬に、旅から戻った一茶が馬橋を訪れたとき、立砂は病床にあり、一一月二日に死去してしまったのです。再度の花見は、かないませんでした。立砂の臨終に立ち会った一茶は、次の句を詠んでいます。
炉のはたや よべ(夜方)の笑ひが いとまごひ(暇乞い)
夜の立砂邸の炉端で、二人で再会を祝って笑い語り合ったのが今生の別れになってしまったという、一茶の哀惜の思いが表れています。立砂は、一茶の心の友でした。