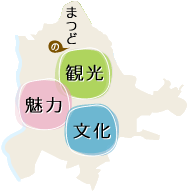水とみどりと歴史の回廊マップ(小金北地区)~Part2~
更新日:2013年11月25日
7.法峯山 華厳寺(ほうぶざん けごんじ)
![]()
真言宗豊山派の寺院で、本尊は地蔵菩薩。火災を防ぐ神通力をもつとされる火防地蔵(ひぶせじぞう)です。この地蔵は、鎌倉時代の寄木造りで、約700年前に幸田の人々が幸田川(現坂川)より引き上げたものであると言われています。
毎年、1月2日には、火渡祭が行われ各地から参詣者が訪れます。また、境内には、松戸七福神の弁財天を祀っています。


松戸七福神「弁財天」
8.聖泰山 長養寺(しょうたいさん ちょうようじ)
![]()
曹洞宗の寺院で、本尊は釈迦如来。下総国三十三ヶ所観音霊場の第十番札所になっています。境内には、「聖徳太子」「白楽天玉宮」の石碑や、観音経を意味する「普門品万巻(ふもんぼんばんかん)」と刻んだ庚申塔などが立っています。

9.幸田貝塚
![]()
この貝塚は、6千年前の縄文時代前期に形成された貝塚です。発掘調査の結果、竪穴式住居跡が165軒発見され、多量の土器や石器、獣や魚の骨、炭化したクルミなども出土されるなど、この貝塚が大集落に伴うものであることが明らかになりました。特に、多種多様な縄の文様を施した「関山式」と称される土器群は縄文時代の土器研究上重要なもので、一部は、松戸市立博物館で見ることができます。

10.香取駒形神社(かとりこまがたじんじゃ)
![]()
祭神は、下総国一宮の香取神宮の祭神で、経津主命(ふつぬしのみこと)の分霊と、神霊の乗る御神馬(ごしんめ)の合祀です。経津主命は、航海の神、武勇の神であり、駒形は、神の乗った神馬の足形を示すもので、神の降臨した神聖な場所とされています。社殿前には、大杉神社と稲荷大明神が祀られています。また、社殿の左手には、江戸時代の年号を刻んだ多数の石祠や庚申塔が並んでいます。

11.長谷山 本土寺(ちょうこくさん ほんどじ)

建治3年(1277年)源氏の名門平賀家の屋敷跡に、日蓮六老僧の一人の日朗上人を導師として招き、開山しました。日蓮宗の名高い寺で、池上の長栄山本門寺、鎌倉の長興山妙本寺とともに日朗一門の三長三本と呼ばれています。


【秋山夫人】
天正10年(1582年)織田・徳川連合軍による長篠の戦いの後、甲斐武田氏滅亡の際に、武田氏家臣の秋山家の娘を養女として徳川家康の側室に仕えさせました。秋山夫人は、浜松城で、家康の五男(信吉)を生みます。家康は、信吉に名門武田氏の家名を継がせて、小金の地に、満七歳になったばかりの武田信吉を三万石として配置しました。

秋山夫人(於都摩)の墓所
【本土寺の重要文化財】
国の重要文化財や県・市の有形文化財などを数多く保有し、梵鐘(ぼんしょう)(国の重要文化財)は、鎌倉時代の建治4年(1278年)の銘があり、大福寺(佐倉市)から移されたもので、県下では、二番目に古いものです。なかでも、本土寺過去帳(県の有形文化財)は、室町時代初頭から江戸時代初頭までに発生した事件が記されていて、松戸市域の中世史を知るための貴重な資料です。

12.本土寺旧参道(日上之松跡)
徳川家康の側室、秋山夫人(於都摩・おつま)はもともと体が弱く、天正19年(1591年)24才で病死しました。そして、本土寺参道脇に、「日上之松」を植えて葬られました。
その後、寛永10年(1633年)から松戸は水戸家の御鷹場預かり所となり、徳川光圀が「日上之松」を見つけて於都摩の葬られている場所であることを知ります。そして、松の根本を人足20人が掘り返して遺骨の捜索をしましたが発見できませんでした。そのため、光圀は墓土を桶に入れ、本土寺本堂東側に立派な墓石を建立して埋葬し、参道両側には、松や杉を寄進しました。
【景観重要道路】
この地域は、今でも往時の趣が残り、本土寺旧参道は、歴史的景観を有する代表的な資源となっていることから、景観重要道路に位置付けています。
この風景をいつまでも大切にし、さらに魅力溢れる地域にするため、周辺の建物も街並みとの調和に配慮してください。

本土寺旧参道

参道脇の秋山夫人(於都摩)石碑
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。